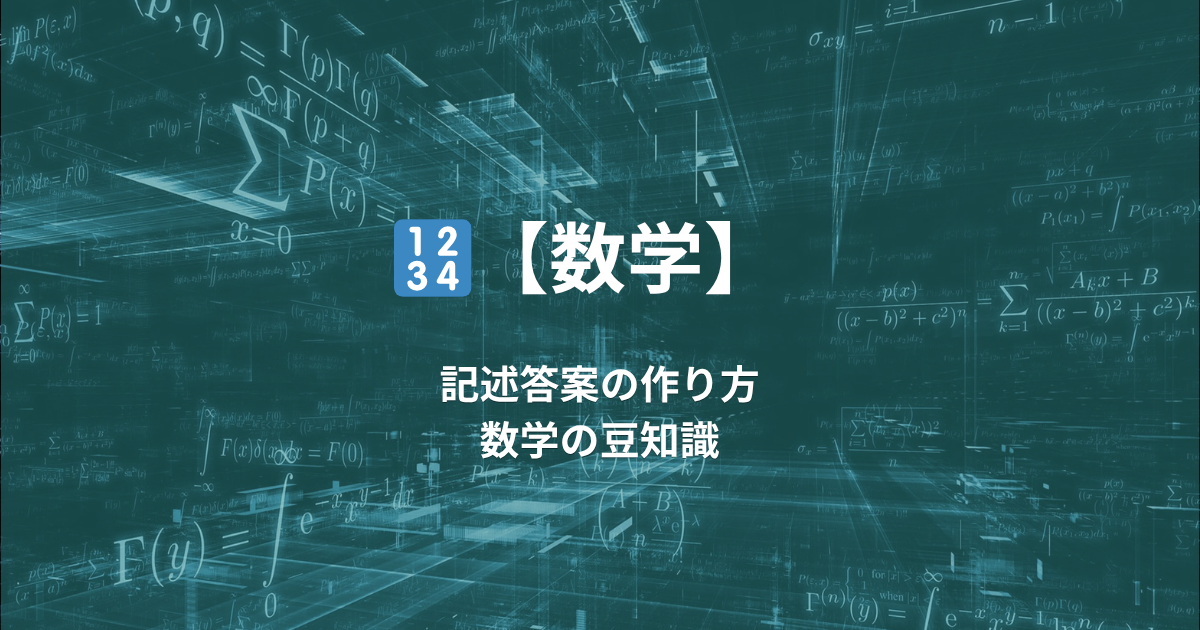導入
数学の記述答案においては、与えられた問題に対しての自分の解答を「正確な論理で」伝えることが重要になってくる。
また、難しい問題になればなるほど記述量が多くなる傾向もあるため、そんな場合でも考え方の筋道などが第三者から見てもわかりやすいような解答を作ることも大事である。
今回は、これらのことがうまく出来るようにするためにいくつかのポイントを知ってもらう。
日本語で説明する
数学の記述解答を作成する際に、文章の大半が数式で日本語がほとんど使われていないという人が一定数存在するが、それは避けるべきである。
理由はいくつかある。
① 採点者から見て論理の筋道がわかりにくい
②自分が見返したときに論理の筋道がわかりにくい
③自分の中で理解していなくてもごまかせてしまう
こういった理由から、日頃の勉強においても記述答案は日本語の説明も込めて作るようにしよう。
図を使う
日本語を用いて考えを説明する中で適宜図も併用すると、より分かりやすくなったり簡単に説明ができるようになったりする。
実際図形やグラフが絡む問題ではもちろんのことだが、例えば確率漸化式の問題でも遷移図と呼ばれるものを用いることで状態の遷移が分かりやすくなる(詳しくは「遷移図 確率漸化式」のようにして調べてもらいたい)。
式に番号付けをする
何度も出てくるような式に対しては、番号をつけることで煩雑を避けることが出来る。
具体的には以下の記事における解答を参考にしてもらいたい。
(上級者向け)同値変形を上手く使う
式変形の過程で同値を表す記号「\(\Leftrightarrow\)」を使うことで、ある程度日本語を省略しつつ客観的にも分かりやすい記述解答を作ることが出来る。
ただし、これを使うと採点者の(解答の論理関係についての)目がより厳しくなることから、論理に自信のある人だけ使うことをおすすめする。
(上級者向け) 上手くごまかす
問題演習をしていると、「(一般的な)高校数学の教科書に載っていないような概念を使って(別解的な)答案を作成したい!」という場面に出くわすことも少なくない。
例:ベクトルの外積、コーシー・シュワルツの不等式、イェンゼンの不等式、テイラー展開など
しかし、これらの概念は入試において使うことが認められていない。
そこでこれらの定理の適用により見つけた答えを、記述答案上ではあたかも偶然見つけたかのように装うことで減点を回避するという方法がある。
その例を見てみよう。
例題1
2つのベクトル\((1,2,3), (-1,0,2)\)に直交するベクトルを1つ求めよ。
方針
解答を書く前に、直交するベクトルの一つが\((4,-5,2)\)であることをベクトルの外積を用いて確認しておく。
解答
ベクトル\((4,-5,2)\)は\((1,2,3), (-1,0,2)\)と直交する。
(実際に内積を計算すると、前者は\(4\cdot 1+(-5)\cdot 2+2\cdot 3=0\), 後者は\(4\cdot (-1)+(-5)\cdot 0+2\cdot 2=0\)となるため)
よって、求めるベクトルの一つは\((4,-5,2)\)である。
補足
この解答では「ベクトルの外積」という言葉を全く使わずに高校数学の範囲内の知識のみを使用して、正確な論理に基づいて解答を作成していることから減点される要素はない。
例題2
すべての正の実数\(x,y\)に対し、\(\sqrt{x}+\sqrt{y}\leq k\sqrt{2x+y}\)が成り立つような実数\(k\)の値の最小値を求めよ。(1995 東大)
方針
コーシーシュワルツの不等式\((a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq (ac+bd)^2\)(等号成立は、\(a:b=c:d\))において、\(a=\frac{1}{\sqrt{2}}, b=1, c=\sqrt{2x}, d=\sqrt{y}\)とおくと、不等式\(\frac{3}{2}(2x+y)\geq (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2\)が得られる。
よって、\(\sqrt{x}+\sqrt{y}\leq \frac{\sqrt{6}}{2}\sqrt{2x+y}\)となる。
(等号成立は、\(\frac{1}{\sqrt{2}}:1=\sqrt{2x}:\sqrt{y}\), すなわち\(y=4x\)のときである。)
これより、\(k\)の値の最小値は\(\frac{\sqrt{6}}{2}\)となることが分かった。
よって、\(k\)の値の最小値が\(\frac{\sqrt{6}}{2}\)となることを、コーシーシュワルツの不等式を直接根拠として使わずに解答を作れば良い。
解答
\(x=1,y=2\)のときを考えると、(左辺)\(=\sqrt{1}+\sqrt{4}=3\), (右辺)\(=k\sqrt{2\cdot 1+4}=\sqrt{6}k\)であることから、\(k\geq \frac{3}{\sqrt{6}}\), すなわち\(k\geq \frac{\sqrt{6}}{2}\)が必要。
ここで、\(k=\frac{\sqrt{6}}{2}\)のときに不等式が成り立つことを示す。
\(k=\frac{\sqrt{6}}{2}\)のとき、
\((右辺)^2-(左辺)^2\)
\(=\frac{3}{2}(2x+y)-(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2\)
\(=2x+\frac{1}{2}y-2\sqrt{xy}\)
\(=(\sqrt{2x}-\sqrt{\frac{y}{2}})^2\)
\(\geq 0\)
よって、もともと両辺が正であったことにも注意すると、\((左辺)\leq (右辺)\)が従うことから、\(k=\frac{\sqrt{6}}{2}\)のときも成り立つ。
したがって、求める\(k\)の値の最小値は、\(k=\frac{\sqrt{6}}{2}\)
補足
コーシーシュワルツの不等式であれば証明も比較的簡単にできることから、上のようにしなくても不等式を証明してから直接使うという手法をとっても良い。
まとめ
せっかく最終的な答えが合っていても、途中の記述で減点されてしまってはもったいない。
この記事に書いてあることを参考にして、減点のない記述答案を目指して日頃から勉強してみよう!
※この記事群は【教科別ミニ読み物】の一部です。
他教科のミニ読み物は、まとめページからご覧いただけます。