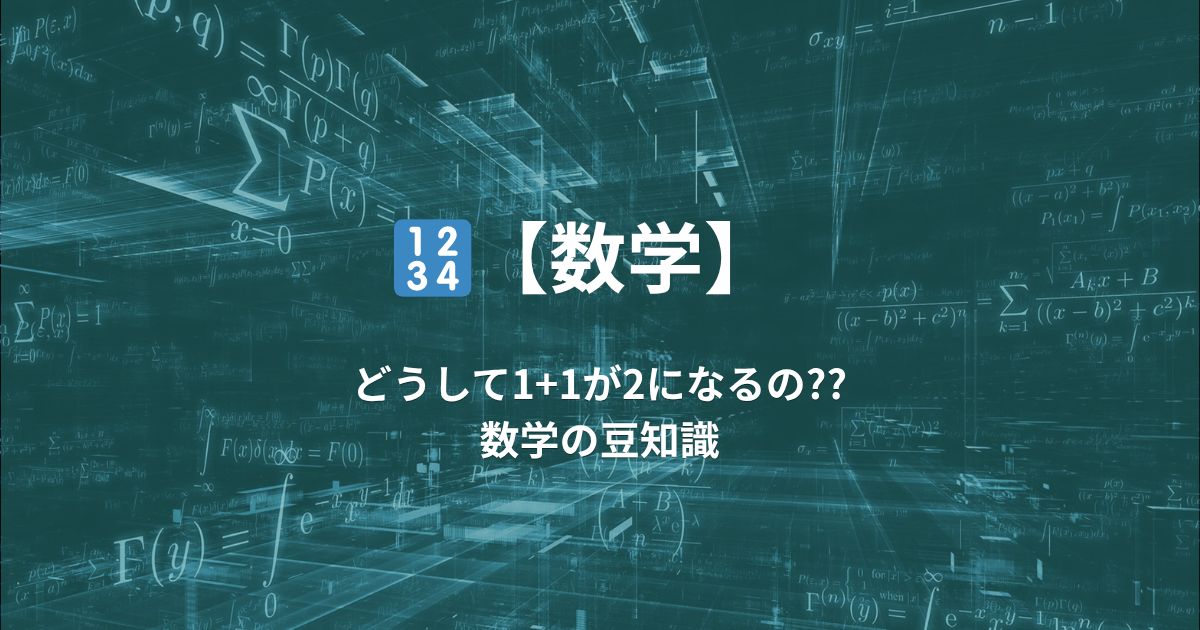導入
突然ですが、皆さんは1+1が2になる理由を説明できますか?
「リンゴ1個とリンゴ1個を合わせたらリンゴ2個になるから…」という説明はとても直感的で分かりやすいのですが、「そもそも1や2というのはどういった数字なのか」ということまで考え始めると、上の説明では不十分になってしまいます。
実は、これらの疑問に答えるためには少しだけ大学数学の世界に踏み込む必要があります。
今回は大学数学を用いて1+1が2になることをきちんと証明してみましょう!
ペアノの公理
1+1=2 を厳密に証明するには、まずは「自然数」という言葉を厳密に定義し直す必要があります。
ここで、自然数というものをペアノの公理と呼ばれる以下5つのルールを満たすものとして定義します。
ペアノの公理
(1) \(0\)は自然数である。(※高校では0は自然数ではないですが、大学では0を自然数として扱う場合もあります)
(2) もし\(n\)が自然数ならば、その後者\(S(n)\)も自然数である。(※ 直感的には、\(n\)が自然数ならば、その次の数\(n+1\)も自然数であるという意味です)
(3) すべての自然数\(n\)に対して、その後者\(S(n)\)は\(0\)ではない。
(4) 互いに異なる2つの自然数\(m,n\)は、その後者\(S(m),S(n)\)も互いに異なる。
(※ 直感的には、\(m\ne n\)ならば、\(m+1\ne n+1\)という意味です)
(5) 自然数の部分集合\(E\)が、もし2つの性質「\(E\)は\(0\)を含む」と「\(n\)が\(E\)に含まれるなら、\(S(n)\)も\(E\)に含まれる」を満たすなら、\(E\)は自然数全体である。
(※ 直感的には、「数学的帰納法の原理が成り立つ」という意味です)
これら5つの性質を満たす数の集まりを\(\mathbb{N}\)と表記し、\(\mathbb{N}\)に含まれる数を自然数と呼ぶこととします。
ペアノの公理によって新しく自然数を定義し直したことから、今まで当たり前のように使ってきた自然数についての常識は何も使えません。
ペアノの公理に載っている性質以外は使えないということに注意しましょう。
自然数に対する和と積の定義
ペアノの公理によって自然数を新しく定義し直すことができたため、次は自然数の足し算、かけ算を新しく定義し直しましょう。
自然数の足し算「+」の定義
①自然数\(m\)に対し、\(m+0=m\)
②自然数\(m,n\)に対し、\(m+S(n)=S(m+n)\)
自然数のかけ算「\(\times\)」の定義
①自然数\(m\)に対し、\(m\times 0=0\)
②自然数\(m,n\)に対し、\(m\times S(n)=m\times n +m\)
直感的に\(S(n)\)を\(n\)の次の数\(n+1\)のことだと思ってしまえば、自然数の足し算の②は結合法則\(m+(n+1)=(m+n)+1\)のことを言っており、かけ算の②は分配法則\(m\times (n+1)=m\times n +m\)のことを言っています。
(あくまで「直感的」であることに注意。)
証明
数\(1\)と\(2\)を、\(1=S(0)\), \(2=S(S(0))\)として定義する。
(直感的には、「1は0の次の数」、「2は0の次の次の数」という意味)
このとき、
\(1+1\)
\(=S(0)+S(0)\)
ここで、左の\(S(0)\)を\(m\)とおくと、足し算の定義から
\(m+S(0)\)
\(=S(m+0)\)
\(=S(m)\) (\(m+0=m\)を用いた)
\(=S(S(0))\)
\(=2\)
よって、\(1+1=2\)である。
他の計算の証明
例えば、\(2\times 2=4\)であることについては…
\(2=S(S(0)),4=S(S(S(S(0))))\)とすると、
\(2\times 2\)
\(=S(S(0))\times S(S(0))\)
\(=S(S(0))\times S(0) +S(S(0))\) (かけ算の②を用いた)
\(=\{S(S(0))\times 0+S(S(0))\}+S(S(0))\) (かけ算の②を用いた)
\(=\{0+S(S(0))\}+S(S(0))\) (一番左にかけ算の①を用いた)
\(=S(S(0))+S(S(0))\) (足し算の①を用いた)
\(=S(S(S(0))+S(0))\) (足し算の②を用いた)
\(=S(S(S(S(0))+0))\) (足し算の②を用いた)
\(=S(S(S(S(0))))\) (足し算の①を用いた)
\(=4\)
(\(S\)がいっぱいで混乱しますね…)
まとめ
\(1+1\)が\(2\)になる理由をきちんと説明するだけでも面倒な議論が必要だということが分かったと思います。
大学数学では今のように
①前提となるルール(=公理)を定め、
②そのルールからスタートして様々な定理を厳密に証明する。
という流れで議論を進めていくことが基本です。
このように面倒な議論をすることで数学は論理的な学問、平たく言えば「信用できる学問」になるわけです。
※この記事群は【教科別ミニ読み物】の一部です。
他教科のミニ読み物は、まとめページからご覧いただけます。