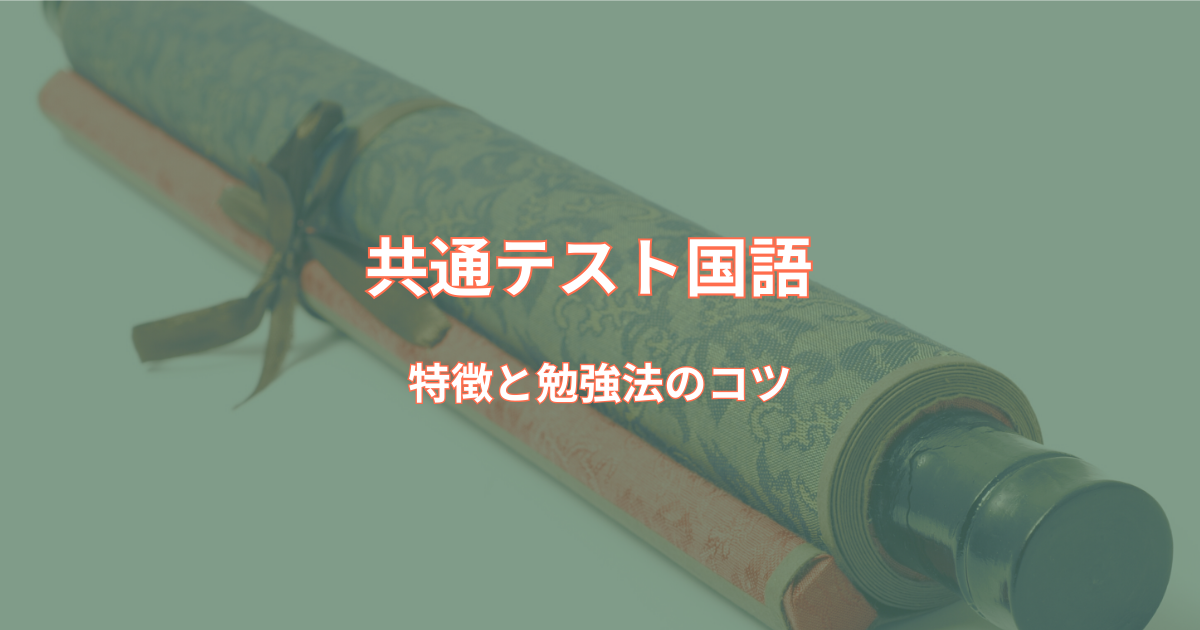共通テストの国語は、大問ごとに出題形式が大きく異なり、それぞれに合った攻略法が求められます。
2025年度からは大問が5問構成に変更され、第3問に図表やグラフを読み取る問題が新設されました国語。試験時間も80分から90分に延長されており、より深い読解力と情報処理力が必要になっています。
試験構成(2025年度以降)
- 第1問:現代文(評論文)
- 第2問:現代文(小説文)
- 第3問:現代文(資料読み取り:図表・グラフ)
- 第4問:古文
- 第5問:漢文国語
現代文(評論・小説・資料読み取り)
特徴
- 論理的な文章や小説を読み、根拠をもとに正しい選択肢を選ぶ形式
- 資料やグラフを読み取り、文章と関連づける新傾向問題も出題
- 文章量も非常に多く、1題にかけられる時間は限られているため、丁寧に読みすぎると時間が足りません。
攻略ポイント
- 本文の根拠を必ず確認する:直感や「なんとなく」で答えず、本文に戻って解答根拠を探す
- 消去法を活用する:選択肢は「間違っている要素」を含むものから消していく
- 漢字問題も軽視しない:漢字は配点ウェイトが意外に高いので確実に得点したい
解説
現代文は、数学のような唯一答えが見えにくいと思われがちですが、共通テストでは必ず明確な正解の根拠があります。正解以外の選択肢には明らかに関係のない情報や間違った情報が含まれています。
特に評論文では、筆者の主張を論理の流れに沿って把握することが不可欠です。
また、小説文では登場人物の心情理解が中心で、想像ではなく本文の描写を根拠にすることが求められます。
古文
特徴
- 架空の学生会話の空所補充など、出題形式が独特
- 基本的な単語・文法・敬語の理解が必須
攻略ポイント
- 語彙・文法を徹底:基礎知識がなければ文章自体が読めない
- 会話形式の問題に慣れる:本文から直接答えを探すのではなく、会話の文脈に合った内容を補う形式が特徴
- 和歌の解釈も頻出:和歌が設問に絡むことが多いので要注意
解説
古文は、「本文を読んで設問に答える」というよりも、解答形式そのものに慣れることが得点への近道です。
例えば「学生の会話形式の空所補充」は、直接本文から答えを抜き出せず、文脈理解や敬語の方向性の把握が必要になります。
語彙や文法を押さえつつ、出題形式に沿った演習を重ねることが欠かせません。
漢文
特徴
- 基本句法や重要語彙を前提に、複数文章を関連づける形式
- 趣旨説明・比較・返り点など幅広い設問が出題
攻略ポイント
- 句法と語彙を確実に:基礎知識がなければ対応できない
- 音読練習が有効:声に出すことで理解が定着し、書き下しや返り点の練習にもなる
解説
漢文は「暗記すれば解ける」と思われがちですが、実際には文章理解があってこそ得点できます。
特に複数文章を関連づける出題では、基礎知識に加え、読解力を問われます。
学習した句法や語彙を繰り返し音読で確認し、解釈力を鍛えることが有効です。
まとめ
共通テスト国語は、「評論・小説・資料読み取り・古文・漢文」と幅広い内容が出題されます。
現代文は根拠をもとに消去法で選択肢を絞り込む力が重要であり、漢字も得点源です。
古文は独特の形式に慣れること、漢文は句法・語彙と読解力の両立がポイントです。
また、理系志望生などで国語が苦手な受験生は、古文や漢文の方が得点力を上げやすいので、まずは古文や漢文から集中的に知識暗記に努めるとよいでしょう。