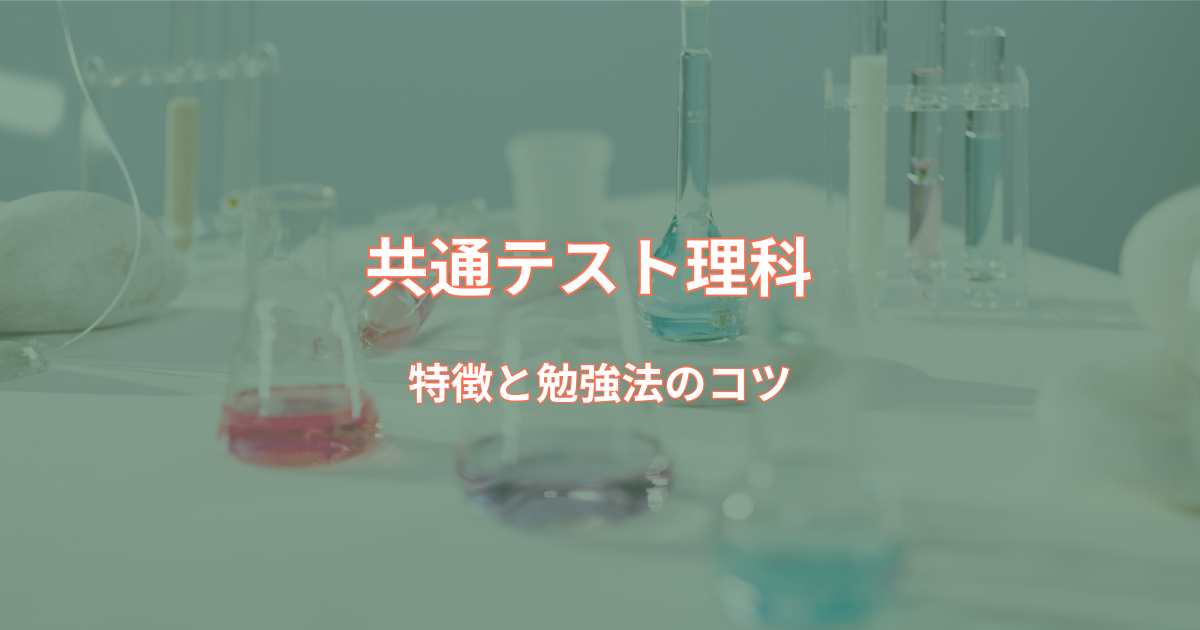共通テストの理科では、従来のセンター試験に比べ、科学的な探究の流れを重視した出題が多くなっています。
単なる知識暗記では対応できず、「資料の読み取り」「現象の理解」「論理的な考察力」が得点の鍵を握ります。
試験の基本構成と特徴
2025年度からは理科の試験時間帯と形式が変更されました。
理科基礎と理科(物理・化学・生物・地学)が同じ時間帯で実施され、最大2科目を選択して受験します。
- 1科目受験:60分/100点
- 2科目受験:130分(解答時間120分)/200点
基礎科目(物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎)は、2分野を選んで60分で解答。
本試験科目(物理・化学・生物・地学)は、より高度な思考・分析を求める出題が中心です。
物理:基礎の理解と情報整理力が勝負
- 問題文が長く、状況把握に時間がかかる
- 公式の暗記だけでは太刀打ちできない
- 実験・考察問題や、見慣れない設定の問題が頻出
共通テスト物理では、物理現象の理解力と読解力が重要です。
基本法則を単に覚えるのではなく、「なぜその法則が成り立つのか」を踏まえて学習することで、未知の問題にも対応できるようになります。
過去問・模試で、長い文章から必要な情報を素早く抽出する練習を重ねましょう共通テスト 対策 理科。
化学:基礎力+考察力の両立が必要
- 教科書レベルの基本事項+思考型の問題が中心
- 公式を当てはめるだけでは解けない計算問題も出題
- 実験結果・グラフ・対数計算などの活用力が問われる
共通テスト化学では、基礎知識の正確性と思考の組み立て力が得点を左右します。
標準問題集レベルをしっかり固めたうえで、初見のテーマにも対応できるようにしておきましょう。
特に「グラフ読解」と「実験考察問題」は重点対策が必要です共通テスト 対策 理科。
生物:知識の理解と考察問題が鍵
- 選択肢の文章を正誤判定する形式が多い
- 実験・観察・遺伝計算など、思考型問題が頻出
- 暗記ではなく「用語の意味と関連性」を理解することが重要
共通テスト生物では、教科書レベルの知識がベースですが、単なる暗記では高得点が取れません。
特に実験・グラフ・遺伝分野は差がつきやすいため、早めの演習と対策が有効です。
知識を関連付けながら覚える習慣をつけ、正誤判定力を高めましょう共通テスト 対策 理科。
地学:資料読解力と考察力がポイント
- 図・地質図・天文計算など、資料をもとに考える問題が中心
- 実験・観察データをもとにした設問が多い
- 「教科書+全統模試」の活用で十分対策可能
地学は、他科目と比べて暗記量は少なめですが、資料の読み取り力が得点の鍵です。
グラフや図から論理的に結論を導く練習を繰り返すことで、安定して得点できます共通テスト 対策 理科。
攻略の基本戦略
- ① 基礎の徹底:公式や知識は「なぜそうなるのか」まで理解
- ② 探究・実験対策:グラフ・資料・会話文など、共通テスト特有の形式に慣れる
- ③ 時間配分の練習:2科目受験では特に「解答順」の戦略が重要
- ④ 実戦演習:過去問+模試+追試で形式に慣れる
共通テスト理科は、「公式を覚える」よりも「現象を理解し、考察する力」が決定的な差になります。
基礎を早期に固め、問題形式への慣れと考察力の強化を同時に進めることが、高得点への最短ルートです。